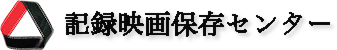詳細
| 番号 | db-00108 |
| タイトル | 神と生きる ~日本の祭りを支える頭屋制度~ |
| タイトル読み | カミトイキル ~ニホンノマツリヲササエルトウヤセイド~ |
| シリーズ |
民俗芸能の心 |
| シリーズタイ |
ミンゾクゲイノウノココロ |
| 時間 | 30分 |
| 色 | カラー |
| 種別 | 35㎜フィルム |
| 製作年 | 2004年 |
| 制作会社 | 毎日映画社 |
| 配給会社 | |
| 監督・演出 | 加藤元康 |
| 企画 | 公益財団法人ポーラ伝統文化振興財団 |
| 脚本 | 加藤元康 |
| 制作(プロ |
橋本淳 |
| キーワード | ポーラ伝統文化振興財団伝統文化記録映画, 民俗芸能の心, 無形民俗文化財, 上鴨川住吉神社の神事舞, 宮座制度, 美保神社の青柴垣神事と諸手船神事, 民俗芸能, 風俗慣習, 祭礼(信仰) |
| 作品補足情報 | 上鴨川住吉神社の神事舞:重要無形民俗文化財(1977年指定) <文化遺産データベース> https://bunka.nii.ac.jp/db/heritages/detail/208290 https://bunka.nii.ac.jp/db/heritages/detail/200136 |
| シノプシス | 日本の祭りを支える「頭屋制度」に焦点を当て、祭りを世話役として仕切る頭屋(宮座も含む)の姿と、祭りを守り、伝えていくための氏子たちの一途な思いを描く。従って、主役は特定の個人ではなく、頭屋制度を受け継いでいく氏子の人たちである。一つ目の祭礼は、島根半島の東端、松江市美保関町の美保神社に伝承されている「諸手船神事(もろたぶねしんじ)」と「青柴垣神事(あおふしがきしんじ)」である。毎年12月3日と4月7日に行われるこれらの神事は、「国譲り神話」、すなわち地上の神であるオオクニヌシ(ダイコク)が、当地「出雲の国」を天から降ってきた神々に譲る神話に基づいている。氏子の中から選ばれた「一ノ当屋」「二ノ当屋」の2人は、青柴垣神事においてミホツヒメ(オオクニヌシの后)とコトシロヌシ(エビス)となり、干し柿以外口にしてはいけない、目を開けてはいけない等、様々な「きまり」が課せられる。神となった2人が行列を伴って海に向かい、囃子が奏されている舟に乗り、海上での擬死再生の儀礼を経て神社の拝殿に迎えられるまでを詳細に記録した。 次に舞台は兵庫県加東市上鴨川の住吉神社に移る。毎年10月第1土・日曜に当地で行われる「神事舞」は、氏子によって組織される宮座(みやざ)の一人が神主を務める芸能であり、こちらにも様々な「きまり」がある。最初の太刀舞(リョンサン舞)は、宮座の「若衆(わかいしゅう)」の序列で、上から三段目のものが舞うという「きまり」がある。また、本作には御神楽(おかぐら)で使用する楽器の一つである小鼓を転がして渡すシーンがあるが、これは手渡ししてはいけないためである。神事舞ではこの他にも、獅子舞、田楽、扇の舞(イリ舞)、高足、能舞(翁舞)といった様々な芸能が披露されるが、これらの練習(はつならし)の風景も収録して、芸能の「きまり」がどのように伝承されているのかをとらえた。 室町時代より続くとされるこれら二つの祭礼。氏子たちは、様々な「きまり」の中で親から子、子から孫へと神事を受け継いできた。次の世代へ、そしてまた次の世代へ。その一途なまでの氏子の姿を通して、「神と生きるとは何か」を問いかける。 |
| 映像内容 | |
| 地域 | 兵庫県, 島根県 |
| チラシ 別データベース |
日本語版チラシあり |
| チラシ画像 |
https://kirokueiga-hozon.jp/chirashi/search/eigadata/view/P-HZ00038 |
| 公開動画 |
|
| ビデオ化・ |
|
| 問合せ情報 |
問合せ先:株式会社 毎日映画社 電話番号: 03-3518-4111 URL:https://www.mainichieiga.co.jp/ |
| 備考 | ポーラ伝統文化記録映画は、ポーラ伝統文化財団にて16ミリフィルム・ビデオ・DVD(一部)の無料貸出を行っています。 http://www.polaculture.or.jp/movie/index.html |